肝細胞がん を学ぶサイト メタボリックは要注意の 肝細胞がん の情報を提供します |
| 肝細胞がん を学ぶサイト |
肝細胞がんの情報を提供します |
|
|
 |
肝細胞癌は肝臓にできる悪性腫瘍である原発性肝癌の約95%を占める疾患です。
肝細胞癌は肝臓にできる癌のことで、肝細胞が癌化し発生するもので胆管細胞が癌化する胆管細胞癌とは区別されます。
原因のとしてはB型肝炎、C型肝炎ウイルスが原因に関係すると考えられていますが、現段階では明確な証明はなされていません。現時点ではB型肝炎ウイルスは直接、発癌に関与していて、C型肝炎ウイルスはウイルスによる慢性炎症を繰り返すことにより、遺伝子の変異が起こり、この蓄積で発癌してくると考えられています。
B型、C型肝炎に罹患している方は肝細胞癌ができやすいハイリスクグループに属してるため、血液検査での腫瘍マーカー、画像診断でのCT、エコーによる定期検診は必要です。これら肝炎ウイルスに感染していない方でも、成人病検診での年一回程度のチェックが重要です。 |
|
|
|
|
肝細胞がん(治療)
|
|
肝細胞がんの主な治療は以下の4つです。
1、肝切除
腫瘍を含む肝臓を切除する手術療法である。切除範囲は腫瘍の位置や広がりによって決定される。正常肝では処理能力にかなりの余裕があるため肝の大部分を切除する手術も可能であるが、肝硬変では肝予備能が低下しているため切除できる量が限られる。肝細胞癌患者の多くは肝硬変がベースにあるため、必要な切除量とのバランスが取れず手術ができないことも多い。また肝外転移がある場合は切除による生存期間の延長が見込めないため適応にならない。
2、PEIT・MCT・RFA
原理は異なるが、いずれも肝臓に針を刺して腫瘍とその周囲のみを壊死させる方法である。残肝に対する影響が小さいため、肝予備能が低くても施行可能である。ただし腫瘍が大きすぎるもの、数が多すぎるものは適応にならない(一般的には3cm、3個まで)。また主要な血管・胆管に接するもの、心臓・肺に近接するもの、肝表面に突出しているものは技術的に施行が困難である(人工腹水・人工胸水を用いる方法や、腹腔鏡、胸腔鏡を併用したアプローチにより、積極的に治療を行う施設もある)。PEITは,3cm,3個までの肝細胞癌に対する治療成績が手術に劣ることが過去の臨床データの集積により明らかにされた.それ以降,治療法の第一選択として行われなくなりつつある。
3、TAE・肝動注化学療法
手術の適応にならないもの(肝予備能が悪い、腫瘍が肝臓の広範囲に散らばっている、等)に行われるが、肝予備能がある程度悪かったり、多発していても施行可能である。TAEは腫瘍を栄養する肝動脈にカテーテルを挿入し、塞栓物質を流す方法である。腫瘍細胞を栄養するのは動脈のみであるが、正常細胞は動脈と門脈の双方から栄養されるため、TAEによって腫瘍細胞のみをいわば『兵糧攻め』することができる。門脈が閉塞している場合などは正常細胞も影響を受けるため基本的に適応外となる。このTAEの変法として塞栓物質に抗癌剤(塩酸エピルビシン,マイトマイシンC,シスプラチン 等)を混ぜて肝動脈に挿入したカテーテルから流す方法があり,TACEと呼ばれている.肝動注化学療法は肝動脈にカテーテルを留置し、定期的に抗癌剤(シスプラチン、5-FU 等)を注入する方法である(Low dose FP療法など)。TAEが適応外となる症例に対して行われることが多い。(奏効率は約40%と言われている)また、動注化学療法にインターフェロンを併用する治療法もある(FAIT療法)。以前は肝細胞癌に対するシスプラチンの動注化学療法は保険適応外であったが,2004年6月から健康保険が適応され,保険診療で行えるようになった(ただし、動脈注射用のシスプラチンはワンショットでの投与法しか認められておらず、従来の持続動注が完全な保険適応になったわけではない)
4、放射線療法
骨転移の痛みを和らげる目的で施行され、一定の効果が得られている。 また現在では陽子線や重粒子線による局所療法が臨床応用されており、臨床試験が進行中である。
|
肝細胞がん(症状) |
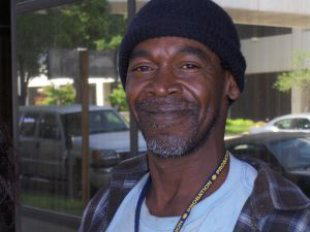 |
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には自覚症状はほとんどないといわれている。病状が進行してくると肝機能悪化および腫瘍の増大に伴い、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、尿の黄染、腹部膨満、腹部腫瘤、腹痛、発熱などが出現してくる。肝細胞癌は多くの場合は肝硬変を持つ患者におこり、症状や兆候は肝硬変の進行を示唆するものとなるので非常に発見は難しい。腹痛や上腹部の腫瘤は所見として取れる可能性はある。肝臓上に摩擦音や雑音が聞えることもある。また血性腹水が認められることもある。AFPが500ng/mlといった所見は非常に肝細胞癌を疑わせる。というのも転移性肝癌ではAFPは低めになるからである。しかし早期肝細胞癌ではAFPが上昇しないことも多い。そのため慢性肝障害の患者は定期的にCTやエコーを行う必要がある。日本において最も多いHCVによる肝硬変の場合はインターフェロン投与で肝細胞癌の発生を減少させる可能性があることが最近わかっている。また頻度は低いが腫瘍随伴症候群がおこることもあるとされている。下痢(血管作動性腸管ペプチド)や高脂血症、低血糖、多発性筋炎、後発性ポルフィリン症や異常フィブリノーゲン症、高カルシウム血症、赤血球増加症などがおこることもある。 |
|
肝細胞がん(予後) |
|
|
肝切除もしくはPEIT・MCT・RFAが可能であった場合の予後は比較的良好で、5年生存率は50〜60%である。しかし、これらの治療の適応にならなかった場合の予後は悪く、5年生存率は10%程度にすぎない。肝細胞癌は慢性肝炎を母地として発生するため、ひとたび治療が完了してもその後に新たな癌が発生してくる確率が高い。癌の発生を早期に発見し、繰り返し有効な治療を行うことができるかどうかが予後を左右する。
またインターフェロンによる肝臓癌の再発予防も研究されている。
|
すい臓がん がん情報 産み分け研究室 膵臓癌 女性の健康 心筋梗塞 脳梗塞 産後
芸能人 男女の産み分け 食道がん 肝細胞がん 前立腺がん 子宮がん 大腸がん 卵巣がん
|
 |
| Copyright (C) 2007 肝細胞がんを学ぶサイト All Rights Reserved. |